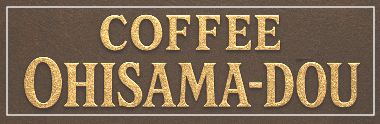霊素「カフェイン」の書 ― 珈琲と健康の調和

霊素「カフェイン」の書 ― 珈琲と健康の調和
序:その名をめぐる誤解
「カフェインは身体を害す毒である」
「夜に口にすれば眠りを奪われる」
――多くの旅人が一度は耳にしたであろう言葉。
しかし、その印象には誤解が含まれる。
カフェインとは、正しき摂り方をすれば日々の暮らしに寄り添い、役立つ霊素。
本章では、その基本から効能、そして上手な取り入れ方を明かそう。
第一醒:「カフェイン=悪しきもの?」その像の修正
カフェインは、珈琲豆や茶葉に宿る天然の苦味精霊にして、眠気を払い、集中を高める力を持つ。
一方で「眠りを妨げる」「胃に負担をかける」との声もある。
だが実際には、量と刻(タイミング)を守れば、多くの者にとって安全であり、むしろ有益である。
その働きは覚醒作用のみならず、血流の促進、気分の改善、代謝の向上といった恩恵へと広がる。
第二醒:カフェインのはたらき ― 心身に及ぶ作用
この霊素は中枢神経に触れ、我らの体に以下の変化をもたらす:
眠気を抑える(覚醒の術) 脳内に潜む“眠りを誘う物質”アデノシンの力を封じる。- 集中力・注意力を高める
心を引き締め、疲れや重圧に強くなる。 - 利尿・血管拡張の作用
血の巡りを良くし、一時的に血圧を上げることもある。
ただし敏感なる者は、震えや不安感といった副作用を覚える場合もある。
すなわち、己の体質に合わせた“ほどよき加減”が肝要なのである。
第三醒:一日に許される量
厚生労働省や世界保健機関(WHO)の記録によれば、健常な成人においては一日400mg以内――すなわち杯にして3〜4杯(1杯=150〜200ml)が指標とされる。
妊婦や授乳中の者、霊素に敏感な者は200mg以内にとどめるのが望ましい。
第四醒:焙煎度と抽出術による変化
「深煎りは苦きゆえ、霊素もまた強し」と思う者は多い。だが実際には、焙煎の炎が進むほどカフェインはわずかに減じる。
これは加熱による分解や、水分と重量の変化によるものである。
より大きな影響を与えるのは抽出の術式である。
抽出法と焙煎度によるカフェイン量(mg)
| 抽出法 | 浅煎り | 中煎り | 深煎り |
|---|---|---|---|
| 滴下(ドリップ) | 95 mg | 90 mg | 85 mg |
| 浸漬(フレンチプレス) | 105 mg | 100 mg | 95 mg |
| 圧縮(エスプレッソ30ml) | 63 mg | 60 mg | 58 mg |
| 冷浸(コールドブリュー) | 70 mg | 65 mg | 60 mg |
(※上記はいずれも150mlあたりの平均値、エスプレッソは30ml換算)
つまり「量が少ないから安全」「時間をかけたから控えめ」とは限らず、飲む量と濃度の均衡こそが鍵となる。
第五醒:デカフェという別の道
夜に飲みたい者、身重の者、安らぎを求める者には「デカフェ」――霊素を抜きし豆――が広く用いられるようになった。
その術法は次の三つに大別される:
- 水抽出法:風味を守りつつ、霊素を浄化する方法。
- 有機溶媒法:化学の力で除去する術(残留管理が要)。
- 超臨界二酸化炭素法:高価だが、風味をほぼ失わぬ最新の術式。
かつて「物足りない味」と評されたデカフェも、今では高品質なスペシャルティ等級が増え、夜の杯や眠りの前の癒やしとして楽しめる。
第六醒:刻と場に応じた選び方
飲む時刻や体調に応じて、杯を選ぶのもひとつの術である。
- 朝(暁の刻):スノートップ(浅煎り)
澄み切った酸味と透明感。目覚めに最適な一杯。 - 昼(日中の刻):コロンビア(中煎り)
甘味と香味の均衡。食後や気分転換にふさわしい。 - 夜(宵の刻):デカフェ・エチオピア(中浅煎り)
フローラルな香気を持ち、眠りを妨げぬ穏やかな一杯。
🏺 結びの巻:調和の秘訣
カフェインは敵にあらず。大切なのは摂取量と刻、そして己が身体との均衡である。
気になる時は控えめに。
力を求める朝はしっかりと。
安らぎを求める夜はデカフェを。
“ほどよく楽しむ”ことが、珈琲のある暮らしを豊かにする秘術。さあ、汝自身のリズムにかなう一杯を見出すのだ。
※ カフェインと眠りの関係について知識を深めたき者には 『《眠れる獅子の調律書》珈琲と眠りの魔導学』が役に立つであろう。
つづけて、覚醒の章 第二話:霊素を抜かれし珈琲 ― カフェインレスの秘儀 を読む
覚醒の章 トップへ戻る
珈琲叙事詩のトップに戻る
⚠️ 備えの書き付け(免責の注記)
ここに記されたカフェインにまつわる知識は、旅人たちの調べや文献の記録をもとに綴られしものなり。
しかし、これらはあくまで道しるべにすぎず、書き手は癒し手でも薬師でもござらぬ。
ゆえに、各々のからだや暮らしに取り入れる際には、自己の判断と責任にてお試しくだされ。
もし心身に不安や病があるならば、必ず信頼できる医師や専門の治癒師へ相談されることをお勧めいたす。