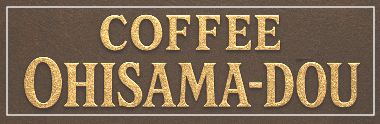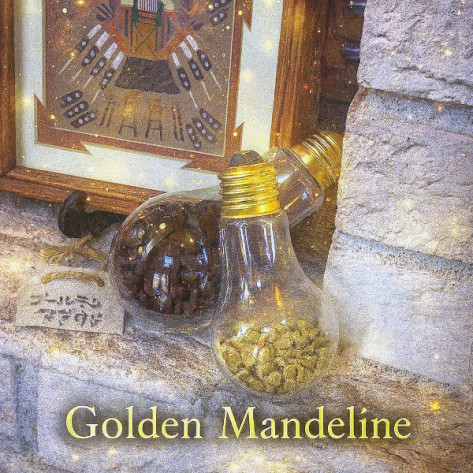《魔導叙録篇》珈琲の歴史 ― 伝説と冒険の飲料

《魔導叙録篇》珈琲の歴史 ― 伝説と冒険の飲料
序:黒き霊薬に宿る物語
いまや世界の隅々に行き渡り、人々に愛される珈琲。
しかし、その一杯の奥には、時代と大地を超えて受け継がれてきた「物語」が潜んでいる。
神話より始まり、宗教・政治・交易・文化を巻き込み、波乱の道を辿ったその歴史は、まさに“冒険の飲み物”と呼ぶにふさわしい。
ここに記すは、その霊薬が我らの手に届くまでの遥かなる旅路である。
第一憶:山羊と修道士の伝説
珈琲の発祥の地は、アフリカ・エチオピアの高地、カファ地方と伝えられる。そこに残るは「カルディ伝説」。
ある日、放牧中の山羊が赤き実を食み、突如として跳ね回り、力漲る姿を見せた。
羊飼いカルディは怪しみ、その実を修道士へと託す。
修道士たちはその実を煎じ、眠気を払い祈りを助ける飲み物として用いたという。
まるで神話のごとき物語なれど、珈琲の歴史はこの“発見”より始まったとされる。
第二憶:アラビアの夜明け ――イスラム世界への拡がり
15世紀、アラビア半島イエメンにて珈琲の栽培と焙煎が始まる。
イスラム教徒は夜の礼拝や瞑想の助けとして、この覚醒の飲み物「カフワ(قهوة)」を愛飲した。
とりわけ名高きはイエメンのモカ港。
ここから出荷された豆は「モカ珈琲」の名を生み、やがて「カフハーネ(喫茶店)」が各都市に誕生した。
友と語り、音楽と詩を楽しむ場として、喫茶の文化は大いに育まれたのである。
第三憶:禁止と拡散 ――数奇なる運命
一方で、珈琲は幾度も“禁令”にかけられた。
宗教指導者や支配者の中には、コーヒーハウスでの集いを反乱の火種と恐れ、禁じた例もある。
だが霊薬への渇望は消えず、豆や苗は密かに運ばれ、イスラム圏の外へと流れ出した。
この時代、珈琲は「魅惑の飲み物」より「政治の道具」へと姿を変えつつあった。
第四憶:ヨーロッパを変えたコーヒーハウス
17世紀初頭、ついに珈琲はヨーロッパに渡る。
最初はヴェネツィアに、その後ロンドン・パリ・ウィーンへと広まった。
ロンドンのコーヒーハウスは“1ペニーの大学”と呼ばれ、商人、政治家、作家、学者が集い、議論し、情報と知識を交わす場となった。
かくして珈琲は、ただの飲み物から「知の象徴」へと昇華していったのである。
第五憶:植民地とプランテーションの影
17世紀以降、植民地支配の広がりと共に、珈琲は世界へ拡散した。
- オランダはジャワ島へ
- フランスはカリブのマルティニーク島へ
- イギリスはインドやスリランカへ
- スペインは中南米へ
こうしてアジア・中南米・アフリカに“生産地”が築かれた。
されどその裏には、大規模なプランテーションと労働の搾取があった。奴隷たちの血と汗が、私たちの「一杯」を形作ってきたのである。
第六憶:日本と珈琲の出会い
日本に珈琲が初めて渡来したのは江戸時代、長崎・出島のオランダ人によってである。
当時は「薬」として用いられる程度に留まり、広く嗜まれることはなかった。
一般に浸透したのは明治以降。
1907年、東京・上野に「可否茶館」が開店、日本初の本格的喫茶店とされる。
その後、戦後のインスタント時代を経て、自家焙煎、スペシャルティ、サードウェーブと、独自の発展を遂げたのである。
※ 日本での珈琲文化の拡がりについては、《魔導叙録篇》―日本に根付いた珈琲の美意識と暮らしもご参照あれ!
第七憶:歴史が語るもの
珈琲は単なる飲料ではない。
宗教・政治・経済・文化――幾多の場面で、人と人を結びつける“媒介”であった。
いま我らが気軽に口にする一杯の背後には、千年以上の物語と世界の営みがある。
それを知れば、珈琲はより特別な光を帯びて感じられるであろう。
🏺結びの巻: 歴史を味わうために
古の物語を体感せんと欲するなら、歴史深き産地の豆を口にするのも一興である。
エチオピア:モカ イルガチェフ:最古の商業産地より届く、奥深き果実の響き。
ゴールデンマンデリン(インドネシア):オランダがもたらした、重厚にしてスパイシーなる一杯。
また、トルコ式の煮出しや、ネルドリップなど伝統の抽出法を試すのも佳き楽しみであろう。
つづけて、記憶の章 第二話:《魔導叙録篇》日本に根付いた珈琲の美意識と暮らし を読む
記憶の章 トップへ戻る
珈琲叙事詩のトップに戻る